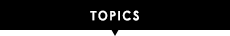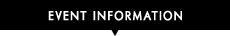TETSUJIN-AUDIO VISUALによる「Star ☆ Jam Street~清掃楽器音楽夢想~」を横浜市立大学附属病院で開催
TETSUJIN-AUDIO VISUALは、髙橋哲人さんとモシ村マイコさんによるアートユニットだ。これまでも音楽や映像と、楽器を用いたアートプログラムに取り組んできた。2人が横浜市立大学附属病院の小児病棟で実施したのは、入院する子どもたちに「清掃楽器」を体験してもらうプログラムである。コミュニケーションアートをとおして子どもたちの病院生活をより豊かな時間にと、アートマネジメントオフィス アホイ!の塚田信郎さんが企画・主催した。
「清掃楽器」とは、「はたき」「ほうき」「ちりとり」などの見慣れた掃除道具に、赤外線やジャイロなどのセンサーを組み込み、音が出るように改造した楽器だ。はたきはドラム、ほうきはギター、ちりとりはキーボードとして演奏することができる。
この日のプログラムでは、はじめに髙橋さんとモシ村さんが清掃楽器を演奏した。ほうきギターをエレキギターのように持ちながら、柄の部分を順に触っていくと、かっこいいギターサウンドが飛び出す。ちりとりキーボードは、ごみを集める面がキーボードの鍵盤のように音階を奏でることができる。そしてはたきドラムは、下に振るとスネアドラム、上に振るとシンバルの音がする。それぞれに音程が違う、いくつかのはたきドラムがあるから面白い。いずれもセンサーと組み込まれたプログラムにより、音と同期した映像がプロジェクションで映し出される仕組みだ。本プログラムは子どもが体験するだけでなく、保護者が一緒に参加することもできる。

「TETSUJIN-AUDIO VISUAL」の髙橋哲人さん(右)とモシ村マイコさん(左)。ほうきギターとはたきドラムに合わせ映像も同期する。

ほうきギターとちりとりキーボード。音階が書かれていて、触ると音が出る。

「TETSUJIN-AUDIO VISUAL」の髙橋哲人さん(右)とモシ村マイコさん(左)。
横浜市立大学附属病院で実施した「Star ☆ Jam Street~清掃楽器音楽夢想~」は、2019年11月の3日間、各1時間30分程度、部屋ごとに数名の子どもたちがプログラムを体験した。実演を見てから、軽いリズム運動をした後はたきドラムを手にすると、はじめは戸惑っていたりはにかんでいたりした子どもたちが、夢中ではたきを振ってセッションに参加する――。髙橋さんとモシ村さんのほうきギターやちりとりキーボードと、子どもたちのはたきドラムの共演は、ここが病院の一室であることを一瞬忘れてしまうような盛り上がりを見せた。
「実際に清掃楽器を手に取って音を出してみると、映像とも連動し、聴覚的にも視覚的にもフィードバックがあります。最初はどうして音が出るのか、わけが分からないといった表情の子どもたちが、次第にほがらかになって、楽しんでくれているのを感じますね」(塚田信郎、以下同)

帰るのが名残惜しいように、髙橋さん・モシ村さんとハイタッチをする参加者の親子。
コミュニケーションアートをとおして、子どもたちの病院生活をより豊かに
2016年より、アートに関わるさまざまなマネジメント業務を担っているアートマネジメントオフィス アホイ!代表の塚田信郎さんは、30年ほど企業に勤めたあと、ビジネスの世界で培った経験をアートの世界に活かせると考え、アートマネジメントオフィス アホイ!を設立した。これまで芸術祭やアートイベントの制作、事務局運営などに携わってきたが、これからは自分たちの自主企画にも取り組んでいこうと立ち上げたのが「アート・クリエイティブによる病院内コミュニケーション増進プロジェクト」である。
本プロジェクトは「横浜市立大学先端科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター」並びに「横浜市立大学附属病院」の協力と、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団アーツコミッション・ヨコハマの「クリエイティブ・インクルージョン活動助成」、東方文化支援財団の寄付を得て実現している。感染症の予防などに慎重にならざるを得ない病院内でのコミュニケーションアートの実施は、少し考えただけでもさまざまな制約があることが予想できるが、企業勤務時代に培った塚田さんのプレゼンテーション力や行動力で実施にこぎつけた。
「企業に勤めていた当時、共同研究で病院に2年ほど入っていたことがありました。そのため病院の内情に関する予備知識が、ある程度はありました。2020年のオリンピック・パラリンピックの開催に向け、近年は特に『多様性』や『インクルーシブ』という言葉が聞かれるようになりましたが、主に対象となるのは障害がある方の場合が多いです。一方で、病院の中には入院生活や闘病生活を余儀なくされている方々が大勢いらっしゃいます。忘れられがちですが、ここにも『多様』な方々がおり『インクルーシブ(社会包摂)』な活動ができるのではないかと、今回の企画を立ち上げました。
病院にアートを持ち込み、患者やその家族に癒しを与える『ホスピタルアート』と呼ばれる分野が盛んになっています。ただ院内に展示された絵画作品を鑑賞する受身の体験だけでは、『癒し』は得られても治癒に向けた『活力』は湧いてこないのではないか。老若男女問わず、人に必要なのは、双方向のコミュニケーションであるはず。そこでコミュニケーションアートとそれを生み出すアーティストの力で、多くの時間を病院で過ごしている子どもたちに元気を出してもらおうと、このプログラムを企画しました」

「アートマネジメントオフィス アホイ!」代表の塚田信郎さん
横浜市立大学先端科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センターと横浜市立大学附属病院
今回の企画を実現するために、まずはプロジェクトの実施の協力を得られる病院を探す必要があった。病院での実施のハードルの高さをあらかじめ知っていた塚田さんは、これまでのつながりがあるネットワークからあたるのではなく、「企画に共鳴してくれる病院」という視点でリサーチをスタートした。横浜市立大学にある「コミュニケーション・デザイン・センター(CDC)」の存在を知り、「ここなら親和性が高そうだ」とアプローチをしてみた結果、CDCの武部貴則先生、西井正造先生などの協力が得られることになる。だがCDCの先生たちは研究機関の所属であり、病院の所属ではない。そこでCDCの先生方や産学連携担当の佐藤さんを経由して、横浜市立大学附属病院へとアプローチをしたところ、小児科の教授、伊藤秀一先生の協力が得られることになった。さらにもう一人のキーパーソンがいた。チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の資格をもつ、石塚愛さんである。
CLSとは医療環境にある子どもや家族に、心理社会的な支援を提供する専門職であり、子どもや家族が抱えうる精神的負担を軽減して、主体的に医療体験に臨めるようなサポートをする職業だ。現在、日本にはチャイルド・ライフ専門課程を有する教育機関がなく、CLS認定試験の受験資格を得るためには、北米の大学・大学院で学ぶ必要があるという(参考:チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会)。石塚さんは仕事柄、子どもたちやそのご家族と密接につながっていた。「そういった方に間に入っていただくことで、我々を受け入れてくれる窓口になっていただけたのが大きかった」と塚田さんは振り返る。
じつは取材日のひと月ほど前、プロジェクトすべてのプログラムが中止になってしまうかもしれない事態に塚田さんたちは追い込まれていた。例年、インフルエンザをはじめとした感染症が流行するのは12月からだが、今年は10月の段階で市内の学級閉鎖が相次いだ。そのため11月中に実施を予定していた2組のアーティストによるプログラムも、一度見直しになってしまったという。
「感染症対策の側面から、一度に多くの子どもたちがひとつの部屋に集まるのは許可されない。ではどうするか。病室ごとに時間を区切って、子どもたちに会場に来てもらいプログラムを体験してもらう、いわば病室ごとの『入れ替え制』という方法で病院内を調整してくれたのが、石塚さんでした」
このような病院内における協力体制が、柔軟な対応が難しい病院でのプロジェクト実現を後押しした。
活動をとおして得た手ごたえ
当初の目標だった、プログラムをとおして病院にいる子どもたちの変化に、塚田さんはどのような手ごたえを感じているのだろう?
「先ほど高校生の男の子が参加しに来られました。思春期ということもあり、普段は催しがあっても『僕はいいです』と遠慮をすることが多かったそうですが、今日は気分が乗ったようで『自分は参加しないけど、見に行くだけ』ということで来てくれました。
見ているうちに楽器に触りたくなったのか、手に取って『おー、すげー』と言いながら楽しそうに演奏をはじめました。アーティストの2人も一緒になって、ジャムセッションに発展しました。戸惑いのある子も、実際に手に取って参加して喜びを表現してくれることが、我々の狙いとするところだったので嬉しかったです」

小児病棟に入院する子どもを対象とすることで、少人数の参加者がアーティストとやり取りをしながら密な体験ができるところが、このプログラムの魅力にもなっている。病院では初めてアートプログラムを開催するTETSUJIN-AUDIO VISUALの2人も、子どもたちの笑顔を見て、手ごたえを感じているそうだ。
アンケートでは、体験をとおして調子が良くなった、面白くて元気になったといった声が届いている。保護者からも「子どもが笑顔になった」と喜ぶ声や、自身も楽しめたといった反響が寄せられた。また本プログラムには、病院の先生や看護師さんといった職員の方たちも、何人か参加されたという。「ノリノリではたきドラムを振っている姿を見て、少しは気分転換になったかなと思ったりもしています」と塚田さん。小児病棟に入院する子どもたちだけでなく、そのご家族や職員も、本プログラムをとおして何らかの変化を感じたようだった。
プログラムの今後の展開については「できることなら横浜市内のみならず、県内などにも展開していきたい」と塚田さんは意気込みを話す。だが今回は運よくCDCという組織のある病院とつながることができたが、そういった組織のない医療専門の病院の場合、「アーティストが訪問する」ことそのもののハードルがやはり高い。CLSの資格を持つ方がいない場合にも、どのようにコミュニケーション型のアートプログラムを実施するメリットを伝えていけるか、塚田さんは課題を感じていた。
「今回のプロジェクトの実現に至るまで、いろいろな経験をしました。いくつもの障害やハードルを越えて今日にいたっているので、経験したノウハウをある程度体系化して次に活かしていきたいと考えています。今回ハードルだと思っていたことも、当たり前に対応できるようにしていきたいです」
本プログラムの成果を、数値化して評価することは難しい。「参加してくれた子どもたちの笑顔が何よりの評価」であると塚田さんは言う。子どもたちそれぞれのなかに、掃除道具が演奏できた驚きや、アーティストやほかの子どもたちと一緒にセッションした体験が残っているはずだ。
この日、取材に入っていた東京新聞には、約5段に及ぶカラー写真入りの大きな記事も出た(2019年11月20日付)。メディアからの反響もあり、周囲の関心も高まるプロジェクトだが、来年度以降もどのように継続していくことができるか。アートの領域から、医療の領域へのアプローチに期待が寄せられている。
取材・文:及位友美(voids)
写真:大野隆介
【プロフィール】
塚田信郎(つかだ・のぶろう)
横浜市在住。長年の大手情報機器メーカー勤務を経て、2016年にアートマネジメントオフィス アホイ!を夫婦で設立。アートとビジネスの間にある「隙間」を埋めることを柱に、若手作家の発表機会の創出、芸術祭やアートイベントの制作、運営等の活動を行っている。