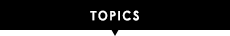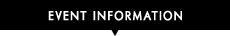ベルサイユ宮殿で行われたオラファー・エリアソンの個展では、滝をモチーフにしたインスタレーション「 Waterfall, 2016 」が設置された。
Photo by: Anders Sune Berg

スタジオには文化や出身地の違う様々な人々が共に働いている。
photo by: Studio Olafur Eliasson.
今回のヨコハマトリエンナーレ2017に作品「Green light – アーティスティックワークショップ」を出品するアーティスト オラファー・エリアソン。
彼のスタジオはベルリン(ドイツ)、コペンハンゲーン(デンマーク)にあり、その中でもベルリンのスタジオは最も大きく、ここに集まるスタジオメンバーは90人を超えます。
私たちはSHIMURAbrosという姉ユカと弟ケンタロウというアーティスト二人のユニットで、「スタジオ・オラファー・エリアソン」で研究員をして3年になります。アーティストとして独立して活動しながら、スタジオでは映像ドキュメンテーションや、その方法を実験しています。
今回は、「Green light- アーティスティックワークショップ」や、その作品が作られる「スタジオ・オラファー・エリアソン」がどのような場なのかについて書いてゆきたいと思います。
ベルリンという街
スタジオ・オラファー・エリアソン(SOE)はベルリンのプレンツラウアー・ベルクという地域にあります。この地域はドイツの中でも最も出生率が高い地域と言われており、午後になれば公園は子供たちで溢れかえります。ベルリンの公園は広く、数もたくさんなのに、それにも増して、子供たちが多いのです。なかなか日本ではみることがなかった光景です。
また、プレンツラウアー・ベルク地域に限らずベルリンは様々な人種が集まっている街です。この街が持つ多様性は、直接スタジオの中にも影響していると感じられます。
スタジオメンバーも、出身国や、それぞれの文化的背景には多様性があります。
よってスタジオ内で話される言葉も様々です。英語を中心として、ドイツ語やデンマーク語、スペイン語、フランス語、日本語を話すメンバーも少数ですが居ます。
多文化、多言語のスタジオの中はとても自由な雰囲気です。裸足で仕事をする人や、ソファでくつろぎながら仕事をする人。食堂にはエスプレッソマシンがあるので、仕事の合間には、そこに集まり、雑談をします。
私たちは、3年前スタジオに来た時、この自由な環境に驚きを感じました。アーティストスタジオというのは常に完璧さを求められる、ストレスフルな環境であることを覚悟していたからです。でも実際はいい意味で、全く異なりました。
スタジオに子供を連れてきて仕事をするということは、珍しいことではありません。幼稚園や学校が早く終わる日は、午後3時ごろに仕事を終え帰っていくことも普通です。
これは仕事の量が少ないという意味ではありません、仕事をする環境と、時間を決める裁量が各個人にあるという意味です。仕事にまつわるシビアさは、同じようにあるのだけれど、環境をコントロールできるので、ストレスもコントロールしやすいというワークスタイルです。
有機的な系
スタジオに入った当初、オラファーはスタジオにはオーガニック(有機的)な仕組みが必要だというコンセプトについて話をしてくれました。一般的な会社のような組織ではなくて、生物の細胞のような働きをするスタジオの概念です。また、スタジオには私たちのような”外の風”を運んでくる存在が必要だ、とも話してくれました。
困ったのがメンバーの役割を把握することでした。これだけ多人数のチームなのに、いわゆるピラミット型の組織と違って、非階層的で流動的な仕組みなのです。なので、一つのプロジェクトを進める時には、上の役職の者に許可を得るというよりも、同僚間で合意を形成しながら進めてゆくと言った具合です。オラファーもアーティストとして中心にいるだけではなく、皆との話し合いに多くの時間を割きます。

ミーティングをする様子。一番右に座っているのがオラファー・エリアソン
photo by: Studio Olafur Eliasson.
スタジオの仕組み
スタジオは地下一階、地上4階建ての、元ビール工場であった建物です。劇場や、レストラン、ホテルなどが同じ中庭を共有している、文化的なエリアです。
SOEはその働きに沿って、3つのセクションに分かれています。ワークショップ、エキシビジョン アンド プロダクション、リサーチ アンド コミュニケーションです。
そして、このSOEをコアに、建築家セバスチャン・ベーマンを筆頭とする建築を専門とするデザイン アンド ディベロップメント(Studio Other Space) と、 Little Sunというアフリカなどの電気がない地域に太陽電池で光る照明を使って光を配るプロジェクトをしているグループがあります。
スタジオの1階と地下には、ワークショップがあります。木工、金属やガラスを加工する工房のセクションです。ここで作り上げられてゆく、作品の数や大きさを見ているだけで、このスタジオがどれだけ世界に必要とされているかがよく分かります。作品制作だけではなく、スタジオ内の家具などもこのワークショップで制作されています。
また、ここには、実験をするための大きなスペースもあります。美術館で行われる大型のインスタレーションなども、ここでの実験を経て形になってゆきます。美術館のメインの展示スペースに匹敵するこのようなスペースを常設的に持っているということが、オラファーの美術館での展示の素晴らしさと直接的に関係していることは想像に難くありません。
2階にはエキシビジョン アンド プロダクション、リサーチ アンド コミュニケーションがあります。エキシビジョン アンド プロダクションは展示のプランニングを主に行います。時には美術館と密に連携しながら仕事を進めます。このようなチームを自らのスタジオ内に持つことで、オラファーは大きなインスティチューションともヒエラルキーのない関係を築くことができるのです。
リサーチ アンド コミュニケーションは作品のコンテクストについて書いたり、出版、アーカイビングに関わるセクションです。私たちのデスクはここにあります。
オラファーの作品には氷や、霧といった形が変化してゆくメディウムを使ったインスタレーションがあります。このような作品に含まれる時間性や空間性をドキュメントすることは、写真やテキストだけでは難しいので、私たちは映像をつかってドキュメンテーションをしています。
それは、客観的な情報をより多く残すということを超えて、詩的な言語でドキュメンテーションをしておく必要性を、オラファーが感じているからに他なりません。
私たちのスタジオで制作した作品については最後に記しましたので、ぜひ映像をご覧になってください。
3階にはデザイン アンド ディベロップメントがあります。ここは主に、建築のプロジェクトを担う部門です。アイスランドにあるHarpa(コンサートホール)のファサードやデンマークの運河にかかる可動橋Cirkelbroen など、オラファーの作品は美術の枠を広げその外側の領域にまで広がってゆきます。
そして3階にはもひとつ重要なスペースがあります。それはキッチンです。
コミュニケーションとしての食

スタジオでのランチの様子。皆が集まって食事をすると家族のような雰囲気が生まれます。
Photo : Maria del Pilar Garcia Ayensa / Studio Olafur Eliasson
スタジオメンバーとゲストを含めると、約100人のための食事を提供するキッチンは、人々のコミュニケーションにとても重要な役割を持っています。日本語には”同じ釜の飯を食う”と言う表現がありますが、全ての人が一堂に集まり同じ食事を食べることは、親密度を高めるためにとても重要だと言う認識は、スタジオでも共有されています。
厨房ではオラファーの妹ヴィクトリアもシェフとして腕を振るっています。そして、提供される食事はベジタリアン食で、食材は全てオーガニックのものが使われます。このオーガニック食材の概念は、美味しさや、スタジオメンバーの健康のためだけではありません、環境負荷の低い状態で作られる食材を購入することが、社会に対して良い働きをする、ということを期待しているからです。
オラファーの作品には「Ice Watch」のような地球温暖化を表現したものもあるように、キッチンにもそのコンセプトが色濃く存在しています。
私たちも、日本の精進料理をベースとした料理を、スタジオキッチンとともに提供したことがあります。精進料理という食材を無駄にしないコンセプトは、スタジオのメンバーからも深く共感が得られました。
開かれたスタジオ-Open House
オラファーは2017年度のベルリン映画祭の国際審査員でもあります。
ある日、スタジオで女性シェフをテーマとしたドキュメンタリーの上映会がありました。このイベントにはスタジオ外の人々も参加しました、ミシュランの星を持つ格式高いレストランの厨房は戦場のようなところで、性差別について日本よりも敏感な感覚を持つヨーロッパにおいても、男社会が色濃く残っているという内容のものでした。映画の上映の後には、監督を囲んでトークセッションがありました。
スタジオは芸術作品を制作する工房としての機能だけではなく、オラファーがアーティストとして取り組む環境問題や人権というテーマを共有するための場としても開かれています。

「Green light – アーティスティックワークショップ」での場面。TBA21(ウィーン)にて。
Photo: Sandro E.E. Zanzinger
Green light
「Green light – アーティスティックワークショップ」は難民という、社会的な問題に対する一つのプラクティスです。グリーンは象徴的に難民への歓迎を意味しています。
知っての通り、ヨーロッパは主にシリアの内戦に端を発した難民の問題に直面しました。これによってEUの国々の中でも意見の対立を招き、難民に対してネガティブなイメージを持つ人々も生まれてしまいました。
「Green light – アーティスティックワークショップ」はオラファーがTBA21(Thyssen Bornemisza Art Contemporary)とのコラボレーションで考案し、サスティナブルな素材で作られた緑色の光を放つ照明の組み立てワークショップを中心に、語学のワークショップや、避難先の社会で暮らすためのガイダンスを行うワークショップなどを組み合わせて難民たちの受け入れを促進する試みです。
この試みは、ボランティアとしてこのワークショップに参加したり、難民たちが組み上げたグリーンライトを購入することで、すべての人々が参加できる仕組みを持っています。
たとえば、レインボーフラッグを掲げることがLGBTへの意見の表明になるように、私たちはこのライトを窓辺に飾ることで、難民を受け入れる意思を表明をすることができるのです。
難民の問題はヨーロッパだけの問題でしょうか?
オラファーは作品を通して、自らの社会が抱える問題として難民のことを考えるきっかけを作りました。そこから先は、私たちに託されています。
あなたを必要としてしてる人々がいるのです。
地球という一つの空間を共有する市民として、この問題に何ができるのか、そのことについて考え、実践してゆきましょう。
横浜は中華街や、外国人居留地など、多文化を包括して社会を作ってきた歴史があります。この横浜の持つ文化的多元性という素地は、難民の問題を考えていく中で一つの手助けになると、私たちは信じています。
SHIMURAbros のSOEでの作品について
#Reflections
これはベルリン新国立美術館がリノベーションされる前に最後の展示として「Festival of Future Nows」と言う展示をドキュメントした作品です。
この展示ではオラファーが教鞭をとり、クリスティーナー・ヴェルナー、エリック・エリングゼンと共に行なっていたUDK(ベルリン芸術大学)「Institute for Spatial Experiments」と言う教育プログラムの参加者たちによるパフォーマンスやインスタレーションなどを多発的に行いました。新国立美術館にはすでに新しい建物の建築家として選定されたデイヴィッド・チッパーフィールドの巨大な木の杭を使ったインスタレーションがグリッド状に配置されていたので、私たちはカメラを使って、空間をグリッド状にスキャンすることにしました。
また、レンズの前にはオラファーが作品に用いる特殊な光学ガラスをフィルターとして用い、これに反射される虚像と、フィルターを通して見られる実像を同時にレコードすることで、空間を多角的に捉える方法を実験しました。
Reflections – a film by SHIMURAbros from SHIMURAbros on Vimeo.
#X-ray of your house
これは私たちが自作の中で取り組んで来たX線という人間の目には見ることができない光を用いて、オラファーのMOMAでのコミッションワーク「Your House」を映像化しました。
「Your House」は本の形態をとった作品です。ページにはインクによって印刷がしてるのではなく、空白が物理的に切り抜かれています。何ページもの切り抜きが集まった時に、ある家の形がが本の中の空洞として3次元的に現れます。
これを独シーメンスの協力を経てCTスキャナでイメージ化することで、実際の本では開くことができない方向へ、ページをめくってゆくかのような感覚を与える映像になりました。
X-ray Documentation of Olafur Eliasson’s artist’s book Your House.newVer from SOE TV
スタジオについて、もっと、詳しく知りたい方は書籍「Eliasson: Open House」に詳しく書かれています。
http://www.buchhandlung-walther-koenig.de/koenig2/index.php?mode=quick&art=1566723

オラファーとSHIMURAbros
photo by: Studio Olafur Eliasson.
著者履歴
SHIMURAbros(シムラブロス)はユカ(1976年生まれ。多摩美術大学卒後、英国セントラル・セント・マーチンズ大学院にて修士号を取得)とケンタロウ(1979年生まれ。東京工芸大学 映像学科卒)による横浜出身の姉弟アーティストユニット。平成21年度 [第13回] 文化庁メディア芸術祭アート部門優秀賞受賞。カンヌ(仏)及びベルリン(独)国際映画祭での上映をはじめ、国立新美術館(東京)、シンガポール国立大学美術館、台北現代美術館(台)、パース現代美術館(豪)、ミュージアムクォーター ウイーン( 墺)ヘッセル美術館ニューヨーク(米)などで作品を展示しています。2014年にポーラ美術振興財団の助成を受けベルリンへ拠点を移し、現在はオラファー・エリアソンのスタジオに研究員として在籍しています。
http://www.shimurabros.com
http://www.facebook.com/shimurabros
http://www.instagram.com/shimurabros