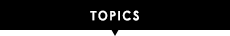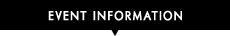Vol.1 横浜美術館の取り組み
Vol.2 横浜市民ギャラリー、横浜市民ギャラリーあざみ野の取り組み
Vol.3 横浜みなとみらいホールの取り組み

横浜能楽堂の子どもへの取り組み
――古典の力がもたらすもの
横浜能楽堂の本舞台は、明治8 年(1875年)に旧加賀藩主邸に建築され、その後大正8 年(1919年)に旧高松藩主邸に移築された「染井能舞台」を復元したもの。140年の歴史を重ねた本舞台は横浜市指定有形文化財だ。能楽堂は1996年の開館、来年は開館20周年を迎える。横浜開港の功労者、井伊直弼の銅像が立つ掃部山(かもんやま)公園内にある。
日本の古典芸能の上演だけにとどまらず、 海外アーティストとのコラボレーションで新しい作品も生み出している。また、解説付きの「普及公演」や、「バリアフリー能」、講座など、多様な取り組みを行なっている。

横浜能楽堂本舞台
「能楽」とは、「能」と「狂言」をひとつにして指す言葉で、600年の歴史があり、「世界無形遺産」にも指定されている古典芸能だ。そんな能楽を現代の子どもたちに伝える企画が、横浜能楽堂で開催された。「夏休み親子能楽ワンダーランド」は横浜能楽堂が年に1度開催している親子のための公演鑑賞とワークショップからなるイベントだ。
午前中には能楽を体験するワークショップが開催された。この日の鑑賞チケットを購入の上、事前に申し込んだ 80人の子どもたちが、「謡(うたい)」「仕舞(しまい)」「狂言」「囃子(はやし)」という能楽の要素ひととおりを体験した。

「夏休み親子能楽ワンダーランド/体験しよう!」
講師を務める若手能楽師集団「七拾七年会」のメンバーが舞台に上がり、能と狂言の所作を教え、参加者がまねをする。能楽の世界では、先生のまねをすることがお稽古の第一歩なのだ 。
囃子の楽器、笛、 小鼓(こつづみ)、大鼓(おおつづみ)、太鼓に実際にふれられるので、子どもばかりでなく付き添った保護者たちにも好評だ。
「小鼓が気に入りました。担ぐのが重くて手は痛くなったけれど」
「笛はなかなかうまく吹けなかったけれどやっと音が出ると嬉しかった」
「大鼓の人がかっこいいなと思った」
など子どもたちは新鮮な体験に目を輝かせた。
 「夏休み親子能楽ワンダーランド/体験しよう!」 |
 |
午後には本舞台で狂言『柿山伏(かきやまぶし)』と能『殺生石(せっしょうせき)』の公演を鑑賞。上演の前に「七拾七年会」のメンバーが客席に向かってミニワークショップと解説を行なって理解を図る。
狂言『柿山伏』 は、柿主に見つかって山伏が言われるままに物まねをする姿が楽しい演目。小学校6年生の国語の教科書にも載っている。
能『殺生石』は、絶世の美女に化けては世の平安を乱す九尾の狐の話が題材だ。「九尾の狐」は最近のゲームのキャラクターとして子どもたちに大きな人気があるのだという。
毎年、子どもにも親しみやすい演目を選んでいるのが特徴だ。
鑑賞を終えての感想からも、
「台詞のすべてはよくわからなかったけど、声のトーンでなんとなく感情が伝わってきた」
「学校の授業で習った柿山伏の本物を観れてとても嬉しかった」
「解説があったのでわかりやすかった。能のストーリーが理解できて嬉しい」
「狂言の声の張りや舞台での響きが素晴らしかった」
などしっかりと古典の世界を受けとめて堪能したことがわかる。
保護者からも「また来年も来たい」との声が多く聞かれた。
狂言を続ける子どもたちも
もうひとつ、横浜能楽堂が開館時から行なっている子どものための事業が、「子ども狂言ワークショップ~入門編~」だ。夏休み中の3日間をかけて、小・中学生を対象に狂言に親しんでもらおうと、開館した1996年から継続して実施している。こちらも30人の募集に対し例年定員を上回る申し込みがあり、抽選での参加となっているという。「子どもに古典芸能を体験させたい」と考える保護者からの申し込みはもちろん、子ども自身の希望による場合も多い。
入門編の初日、子どもたちは、まずは正座してのおじぎの所作から教わる。立ち方、座り方、足の運び方、扇の使い方などを学び、最終日には狂言『柿山伏』の一部を演じるところまでを習う。
講師は、狂言の名門、大蔵流狂言方・山本東次郎家の山本則俊さん、山本則重さん、山本則秀さんだ。

「こども狂言ワークショップ~入門編~」
保護者からは
「子どもが礼儀作法を学べた」
「自分が古典の所作が好きで申し込んだが、子どももどんどんのめりこんだ」
などの喜びの声があり、子どもたちからの声には
「先生が立派な感じで、何でも上手なので驚いた」
「とてもできないと思った舞ができた」
「昔の日本人の気持ちが感じられた」
「もっと狂言が観たくなりました」
など、大きな体験だったことが窺える。
この入門編は一度限りの受講だが、稽古の継続を希望する子どもたちは、1月から開催される「卒業編」を受講することができる。昨年は入門編に参加した子どもたちのうち6名が卒業編に進み、10回ほどの稽古を重ねた上、「横浜こども狂言会」での初舞台を踏んだ。また、ワークショップ卒業生有志が「いろはの会」として稽古を続けている。ワークショップの受講をきっかけに狂言を楽しむ子どもたちが大勢いるのだ。140年の歴史を重ねた本舞台に立つ体験が子どもたちにとっての新しい世界への入り口となっている。
 「こども狂言ワークショップ~卒業編~」 |
 「横浜こども狂言会」撮影:神田佳明 |
このような、子どもたちが古典芸能に接することの意義を、事業担当の石川泰菜さんはこう説明する。「能楽師の方は子どものころから一つの道を極めてきた人。こんな毅然とした生き方をしている大人がいると知り、直に触れること、それが大きな意味を子どもたちにもたらすのではないでしょうか」。
古典芸能の世界に生きる大人の存在感と、その大人から学ぶという体験が子どもの成長に大きく影響するのだと感じた。

(写真提供:横浜能楽堂)
【横浜能楽堂へのアクセス】
住所:〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘27-2
最寄り駅:JR ・横浜市営地下鉄線「桜木町」駅、京浜急行線「日ノ出町」駅
お問い合わせ:TEL 045-263-3055
http://www.ynt.yaf.or.jp

横浜にぎわい座の子どもへの取り組み
――大衆芸能パワーを生かす
「横浜にぎわい座」の開館は2002年 。その芸能ホールは、やぐらをイメージした舞台廻りや桟敷席、仮設花道など大衆芸能の雰囲気に満ちている。ここでは落語、講談、漫才、マジック、民謡など様々な公演が毎月1日~15日に開催されている。
子どもたちにとってテレビで観るお笑い番組にはなじみがあるだろうが、生の落語を聴くことはどんな体験となるのだろうか?
8月2日、「夏のこども寄席」が開催された横浜にぎわい座。小中学生料金(500円)が設定されていることもあって、大勢の子どもの姿で芸能ホールやロビーはあふれていた。「こども寄席」が開かれるのは年に1回。子どもでもわかりやすい演目の落語が並ぶ。子どもが主役の『牛ほめ』、おなじみの昔話を題材にした『桃太郎』、食べ物にまつわる『そば清』。そもそも演目名をあらかじめ知らせること自体が「ネタ出し」と呼ばれる異例の配慮だ。「色物(いろもの)」と呼ばれる落語以外の芸では「曲独楽(きょくごま)」に「動物ものまね」と幅広い年齢層に受ける伝統芸が披露される。

親子連れや、また祖父母とともに三世代での来場も目立つ。思い思いのお菓子や飲み物、お弁当を持ってきて、食べながら飲みながら開演を待つのも演芸場ならではの気軽なしきたりだ。客席の両脇にある桟敷席も親子で横並びできるため大人気だった。
幕が開き、最初の落語の「枕(まくら)」(本題に入る前の冒頭のとっかかりの話)で、扇子や手ぬぐいの使い方など落語特有の仕草の説明があると、子どもたちが身を乗り出した。一気に惹きつけられたようだ。
また、「曲独楽」では、会場から2名の子どもが参加、ステージに上がり「糸わたりを披露し、大きな歓声に包まれた。
 |
 |
お腹の底から笑って満足げに帰途につく子どもたちからは「初めて聞いた落語はとても面白かった」、その保護者からは「子どもと一緒に大人も楽しめてよかった」という声が聞かれた。
また、文化庁委託事業として、施設近隣の小学校の4~6年生を対象に「寄席体験プログラム」も実施している横浜にぎわい座。 落語がどんなものかを説明する講座や、鳴り物(出囃子の太鼓や三味線)の体験プログラムも組み入れて、落語を聞く。2005年度から開始した事業で、昨年度までにのべ122校が横浜にぎわい座を訪れた。多くの子どもたちが落語に触れている。
「二ツ目などの若い落語家さんの中にも、とても人気も実力もある方がいます。そういうお気に入りを見つけにいらしていただくのもいいですね。絶妙の仕草や表情、話芸で想像力を刺激されながら、人の話を聴くこと、親子で一緒に笑うことの楽しさをぜひ味わってほしい」と事業担当の 墻内(かいと)美穂さんは言う。
大衆芸能が昔から盛んだった横浜。気さくな雰囲気の中で、現代の子どもたちが生の話芸のすごさや、ときに古い日本語にもふれて、周囲の大人たちと一緒に声を上げて笑うことを生活に取り入れられたらもっとのびのび過ごせるのでは、と大衆芸能のパワーを感じた。

【横浜にぎわい座へのアクセス】
住所: 横浜市中区野毛町3丁目110-1
最寄り駅:JR線・市営地下鉄線「桜木町」駅、京浜急行線「日ノ出町」駅
お問い合わせ:TEL 045-231-2525
http://nigiwaiza.yafjp.org/
Vol.1 横浜美術館の取り組み
Vol.2 横浜市民ギャラリー、横浜市民ギャラリーあざみ野の取り組み
Vol.3 横浜みなとみらいホールの取り組み