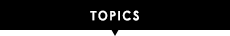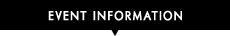懐かしいけど新しい”御用聞き”スタイル
横浜市営地下鉄・片倉町駅から徒歩20分、新横浜駅からはバスで10分。幹線道路脇の味わいのある建物・八反橋フードセンターの中に、「DAILY SUPPLY SSS」は店を構える。可愛らしい看板を見つけ、思い切って自動ドアを通り抜けると、店先からコーヒーの香りが漂う。中で待ち受けているのは、アーティストと建築家の3人による、古くて新しい買い物の形の提案だ。

量り売りメニューは少量から気軽に買うことができる。コーヒーグッズも充実
店内にある商品は、主に4カテゴリーに分かれる。お米やコーヒー豆、ジュース、洗剤などの量り売りの日用品、工芸作家によるガラスのボトルや布団叩きなどの道具類、”アーティストバイヤー”が選んだ海外の日用品、そしてアート作品や古道具。どの商品も、LPACK.がこれまでの活動の中で出会った信頼できる作り手や、この店の理念に共感してくれた企業から取り寄せた、自信を持っておすすめできるもの。一つ一つ商品の説明を受けているだけで一日楽しめるくらい、それぞれにストーリーを持った、個性豊かな品々が並んでいる。
量り売りの商品は、カウンターの後ろにあるストック棚を開け、必要な分だけ取り出してくれる。同じお米でも、ちょっとだけ背伸びして毎日食べたいもの、とても手間の掛かった製法で作られた、たまの贅沢品として味わいたいものなど、どの種類が良いか、どれくらいの量が良いかと聞くうちに、自然とコミュニケーションが生まれる。名付けて「GOYOKIKI Style」だそうだ。

量り売りのために、特別に作られたストック棚。
「もともと市場として人が買い物をしに来ていた場所なので、また人の流れを掘り起こすにはどうしたらいいかということを考えながら、流通システムや買うという行為について知っていくのが楽しいですね。一個一個の商品を見つつ、それを作る人と買いに来る人との関係性をどうやって作っていくか、ミクロとマクロの視点を行き来している感じです」
八反橋フードセンターは、かつては精肉店や生花店でにぎわった、築50年近い元日用品市場だ。ピーク時には横浜市内に約90カ所あったという長屋風の小売商店の集まりは、現在その多くがシャッター街。八反橋では、美容室が営業しているほかは、倉庫等になっている。そうした建物の歴史を汲み、「必要なものを必要な量買いに来るような人の流れが、ここにできてほしい」と小田桐さんは話す。

現在も営業している「ビューティ芙美」の看板だけが光る
子育て世代が発信する“郊外”
ともに黄金町のレジデントアーティストとして活動していたLPACK.の小田桐さんと中嶋哲矢さん、建築家の敷浪一哉さんは、共同アトリエ+コーヒーショップとして使える物件を探していたときに、このフードセンターに出会った。それぞれ小さな子どもを育てる父親でもある3人は、子どもができてから、行動パターンが変わったという。

「車移動が多くなるので、駅前であることより、車で行きやすいことのほうが重要になってくる。ここにも、敷浪さんは車、僕と中嶋は自転車で通っていますが、3人の家からちょうど中間地点くらいにあたるので、無理はまったくしていないんです」

DAILY SUPPLY SSSへは、店の脇からも入ることができる
一般的な不動産の価値観ではなく、自分たちのライフステージと、表には出てこない、日常と地続きの面白いスポットを探したいという意欲に合わせ、”郊外”という舞台を選んだ3人。始めはこんな所でお店をやるのかと驚いていたオーナーも、少しずつ姿勢が変わってきているのだという。
「通路をちょっときれいにしたり、外壁や天井・屋根の塗装をしたり、看板も変えようかなと相談してくれたり。僕らが入ってきてからまだ一年ぐらいですが、この店 がだんだんと出来てきた中で、この場所への愛着がまた湧いてきているのかなと感じられるアクションが起こっていて嬉しいですね。」

店先には、小田桐さんの地元である青森から入荷したりんごも
子どものお迎えがあるため、営業時間もあえて17時まで。月に一回程度開催しているモーニングタイムは朝7時に始まる。小田桐さんは「ぜひ朝早起きして、ここに来る時間を作ってほしいですね」と呼びかける。
まちに入り、その機能の一部になる
LPACK.はこれまで、国内各地のさまざまなスペースに「コーヒーのある風景」を作るカフェ・プロジェクトや、アートイベントに訪れる人のためのビジタースペースづくり、美術館の教育普及プログラムと連動したワークショップスペースの設計など、アート、デザイン、建築、民藝といった領域を横断しながら、アーティストと鑑賞者、地域の人々とのコミュニケーションの場を創造してきた。

コーヒーを淹れてくれるLPACK.の中嶋さん。焙煎機とお客さんの距離が近い
静岡・浜松の大学では共に建築を学んでいたが、自分たちで設計して図面を引き、建物を建てる建築家にこれからなるということに、実感が沸かなかったという。そこで、人が集まる状況や、そこで何かが生まれようとしている空間も「建築」だと捉え、「コーヒーが『建築』の最小単位なんじゃないか」と考えたところから、既存の建物を使い、コーヒーを淹れる活動がスタートした。
彼らが黄金町エリアマネジメントセンターと2010年〜2012年まで共同運営していた日ノ出町の「竜宮美術旅館」は、戦後間もなく建てられた旅館を再生した、アーティストやまちの人が集うカフェ+展示スペースだった。廃墟となっていたおどろおどろしい建物にアーティストと共に手を入れ、「まちのシンボル」をつくる という意識でやっていたという。

竜宮美術旅館
また、現在名古屋で並行して運営している、元寿司屋に手を加えた「UCO」というスペースは、「社交場」というテーマを設定し、試行錯誤している最中だ。
「活動を始めた当初から、どのプロジェクトでも『まちの機能の一部になる』ことを目指してきました。必要ではないけど、あるとより魅力的になる存在として、まちに馴染んでいく、風景の一つになるというのが、僕らのやりたいことなんです。お店をやれば、体はそこにいますし、パフォーマー的な存在に見える。もちろんそういう意識もありますし、そういう振る舞いもしますが、まずは建物と、そこに持たせた機能があって、僕らはそれを動かす人たちというつもりでやっています。
言ってしまえば、どこでもできるし、何でもやりたいけれど、特に埼玉の『きたもとアトリエハウス』(2012〜2017年)以降は、僕らがいなくても場が動いていくように意識していますね。」

UCO
「UCO」には現在3人のカフェスタッフがおり、建物内ではZINEや什器の制作などを行う5つの”Club”が活動している。置き土産のように、LPACK.が各地につくっていった風景が、まちに少しずつ沁み込んでいる。
アーティストの視点を日常に
「竜宮美術旅館」より前の2009年、第1回目の「黄金町バザール」が終わった後に元鉄板焼き屋だった場所に開いた「L CAMP」では、黄金町のアーティスト約20組が日替わりで店長を務め、料理を振る舞った。「作家と人が、作品以外でゆるやかにつながる場」は、ゲストアーティストに滞在制作先の国の日用品を選んでもらう「アーティストバイヤー」という仕組みで、DAILY SUPPLY SSSでも続いている。

アーテイストの狩野哲郎さんと丹羽良徳さんが「ゲストバイヤー」として買い付けた品々 と、各作家の作品
「アーティストの視点って、直接作品を通して見えるもの以外にも、面白い部分がたくさんある。日用品店に来る、アートに関心のない人たちにもそういう視点を伝えていけるのは、面白いなと思っています。基本的に売れることを第一目的にしていないので、何を仕入れてきてくれるか はアーティストにお任せしていて、僕らも彼らが選んできたもの を見せてもらう瞬間を楽しみにしています。一つ一つ、何で選んできたかという理由が、ちゃんとあるんです。」
現在置いているのは、狩野哲郎さんがアメリカ・ポートランドとシンガポールで買い付けたものと、ウイーンに滞在中の丹羽良徳さんが選んだヨーロッパのもの。現地のスーパーやホームセンター、蚤の市などで手に入れたカラフルな日用品の数々からは、その土地の暮らしが見えてくるようだ。

アート作品も展示・販売する
アート作品も展示し、ギャラリーを通して販売する。アートを買うという行為にも、日用品店に作品を置くことで、一歩近づいてもらいたいと考える。
「ギャラリーまで行って作品を買う人はなかなかいませんし、日用品を買いに来た人が、アート作品に目を向けるまでは、時間がかかるかもしれない。でも、ここを日常的に使っていくようになることで、そこにも気づいてもらえたらいいなと。」
さまざまな角度から、アートを日常空間に持ち込む。空間作りを学びながら、多くのアーティストと関わってきたLPACK.だからこそ、できる取り組みかもしれない。
小さな体験から、意識の変化へ
どの商品も、消費のあり方や、アートとの触れ合いなど、クオリティの高さだけでなく、アイデアを内包するDAILY SUPPLY SSS。そうした提案を、訪れる人々はどのように受け止めているのだろうか。
「まだみんな、僕らが何をやろうとしているのか、探っている段階だと思います。共感してくれる人がどれくらいいるのか、どうやってそういう意識の変化というところにアプローチしていくのかということは、今までやってこなかった新しい取り組みなので、メディアに積極的に出るなど、手探りでやっている状態です。
今はまだ伝えていく段階だと思うので、まずはこういう場所ができたということを知ってもらって、来てもらって、どんなものがあるのかと、使い方を知ってもらう。その後、2回目以降にどうやってつなげていくかですね。最近、よくコーヒーを買いに来るお客さんが、自分の容器を持ってきてくれるようになりました。前にコーヒーを買ってくれた近所のおじさんは、何か袋ありますかって聞いたら、じゃあこれでいいよって、コンビニのビニール袋を出してくれたんですが、僕らはそれでも全然いいんです。エコとかでなく、まずはこういう意識や振る舞いを体験してみてほしい。」

季節ごとに4種類の豆を焙煎する「木同山鳥珈琲焙煎所by.L PACK」。飲んだときに思い浮かべる風景を言葉にし、商品名に
今後は、工芸作家と共に開発するオリジナル商品や、使い心地を”試せる”商品も増やしていく予定だ。店内には、液体石けんのハンドソープを試せるシンクもある。
「食品が試食できるのはもちろん、タオルなども置いて、使い込んだ後の使い心地を試してもらいたい。革の財布のように、長年使うとどうなるかというのも、見せていきたいなと」

量り売りをやろうと決めた際、象徴的な容器をつくり たいと、10年来の知り合いであるRITOGLASSに依頼してできたボトル。この形のものはクラウドファンディングで完売し、もう一つのタイプを店頭で販売する
難しいのは、”どうやって”商品を増やしていくか。ブレない提案のためには、単純に情報だけを見て好みで選んでいくのではなく、そこに確かなストーリーがあることが重要となる。
「ここでないといけないという考えはあまりなくて、こういう場所が、ほかの街でも違和感なくやれるようになっていってほしいなと思います。でも、コンビニやAmazonといった、既存のインフラと対抗するわけではなく、どうやって共存して、補う関係を作っていけるか、考えていけたらいいですね。」
(文・齊藤真菜)
【プロフィール】
小田桐奨(L PACK.)
1984年生まれ、静岡文化芸術大学空間造形学科卒。中嶋哲矢とのユニット、L PACK.にて活動。アート、デザイン、建築、民藝などの思考や技術を横断しながら、最小限の道具と現地の素材を臨機応変に組み合わせた「コーヒーのある風景」をきっかけに、まちの要素の一部となることを目指す。
2007年より活動スタート。主な活動に廃旅館をまちのシンボルにコンバージョンする「竜宮美術旅館」(横浜/2010-2012)や、室内の公共空間を公園に変えるプロジェクト「L AND PARK」(東京/2011-2012)、みんなのアトリエ兼セカンドハウス「きたもとアトリエハウス」(埼玉/2012-)、ビジターによるビジターのためのスペース「VISITOR CENTER AND STAND CAFE」(名古屋/2013)などを展開。また、各地のプロジェクトやレジデンスプログラム、エキシビションにも参加。
DAILY SUPPLY SSS
デイリー サプライ エスエスエス
住所:横浜市神奈川区羽沢町1802-1
アクセス:片倉町駅(横浜市営地下鉄ブルーライン)徒歩20分、横浜駅からバスで八反橋下車すぐ
営業時間:12:00-17:00
定休日:日・月・祝
連絡先:045-516-4829