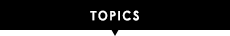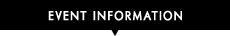©Damien Jalet |Kohei Nawa, VESSEL_2016_Rohm_Theatre_Photo by Yoshikazu Inoue
白紙の状態からスタートした、クリエイター同士のコラボレーション

「SANDWICH」外観 photo : Nobutada OMOTE | SANDWICH
1月某日、京都市の伏見区にあるスタジオ「SANDWICH」にて『VESSEL yokohama』の稽古に入る直前の名和 晃平さんに、スカイプインタビューをすることができた。名和さんがディレクターを務める「SANDWICH」は、建築家、デザイナーなどのさまざまなクリエイターと横断的な創造活動を行うためのプラットフォームとして、2009年からスタートしたスタジオだ。スカイプ越しには大きなテーブルが映る。テーブルを囲み、チームでミーティングをしたりご飯を食べたりしているとスタジオのスタッフが教えてくれた。名和さんが日常的に複数のメンバーと制作をしている様子が目に浮かぶようだ。
名和さんは海外の美術館や国際展にも多くの出展歴をもち、東京都現代美術館で個展(2011)が開催されるなど、名実ともに日本の現代美術界をリードする彫刻家のひとりだ。京都造形芸術大学では教授として教鞭を執っている。名和さんの作品は、ビーズやプリズム、発泡ポリウレタン、シリコーンオイルなどさまざまな素材を用いて、「PixCell=Pixel(画素)+Cell(細胞・器)」という概念を軸にかたちづくられている。その表現の多彩さと鮮やかな造形美は、彫刻の新たな可能性を拡げている。
そんな彫刻家である名和さんが、振付家のダミアンさんとのコラボレーションに取り組んだと聞いて、そこにはどんなきっかけがあったのか興味をひかれた。そもそものはじまりは、「あいちトリエンナーレ2013」で、名和さんが発表した泡のインスタレーション《Foam》を見たダミアンさんが、名和さんに共同制作をオファーしたという。名和さんはどんな感想をもったのだろう?
「ダミアンから長いメールをもらいました。たくさんの考えや想いを伝えてくれたのですが、何を一緒にやれば良いのか、最初はよくわかりませんでした。具体的に彼がこの作品を発表するステージの予定があったわけでもなく、どういう形式でやるかといったことも決まっていなかったんです。
純粋にクリエイター同士のプロジェクトとして、何もない白紙の状態でお互いを知ることからはじまりました。対話を重ねていくことでダミアンがイメージしていることが、つかめてきました。彼は振付家なのでポーズのスタディ写真を送ってきてくれて、それがユニークで面白かったんです。僕自身が彼のイメージをうまく空間に落とし込むことができそうだなと思ったので、コラボレーションを続けていきました。」
アウトプットが決まっているわけではない、純粋なコラボレーション。ある意味ぜいたくなスタートをきった2人の創作だが、初期にはヴィラ九条山というフランス政府が運営するアーティストインレジデンスのプログラムのサポートを受けて共同制作がはじまったという経緯があった。
 photo : Nobutada OMOTE | SANDWICH |
 |
振付家・ダミアンとの創作のプロセス
名和さんが振付家とのコラボレーションに取り組んだのは、今回が初めてのプロジェクトとになる。だが名和さんは学生時代に、田中泯さんが主宰していた「アートキャンプ白州」*に参加し、ダンサーの身体やダンス表現について学んでいたという。
*1988年~98年まで山梨県白州町で開催され、舞踏公演を中心に、美術、演劇、音楽、映像などさまざまなジャンルの表現活動が集い、アートプロジェクトやアーティストインレジデンスの草分けとなったイベント。
「学生時代、基礎課題で木彫とか石彫をつくっていた頃から、ダンスにも興味をもっていて、刺激を受けていました。今の自分が立脚している「表皮」や「cell(細胞)」という概念も、身体とは何か?という問いの探求から抽象化されて至ったもので、そもそもは身体からはじまっています。ダミアンとの共同制作は、自分の原点に戻っていくような感覚がありました。
2015年に『VESSEL』を大阪で最初に発表したときは、まだダミアンが舞台上で何を目指しているかわからないまま舞台美術をつくり、ダンスと美術を合わせてみたという状態でした。でもそこから、ダミアンがやりたいことや、ダンサーをどういうイメージで扱うかといったことをつかむことができました。翌年の京都、犬島、そして横浜へと続く展開では、振付とか舞台美術といった役割分担関係なく、コンセプトやイメージ、シーン展開をディスカッションしながらつくっていきました。」
お話を聞くと2人の創作は互いのイメージを、ディスカッションをとおして発展させていき、理想的な形で結実していったことがわかる。
「ダンサーのポージングは、ダミアンが振付をします。それを空間的に構成したり、ポーズとポーズの間の関係をつくったり、全体のストーリー展開をつくる部分は僕からも意見を出しています。そこに日本神話や、比喩的な表現などが入っていくため、最初のコンセプトの立ち上げもとても重要でした。
『VESSEL』は彫刻的な表現と言える部分もあると思いますが、ダミアンがイメージしていることを実現させるという意識も同時にもっていて、それが一番優先されることだと考えています。僕は舞台上に造形物をつくりますが、ダンサーよりも造形物が目立ってしまうのはよくないと思い、創作の過程では、ダンサーの身体をいちばん美しく効果的に見せる設定を第一に考えました。」

©Damien Jalet |Kohei Nawa, VESSEL 2015 Creative Center Osaka
作品のコンセプトと舞台美術の素材
作品タイトルの『VESSEL』は、器や船という意味を表す。作品のテーマについては、名和さんが自身の創作において取り組んできた「cell(細胞)」という概念に呼応するような形で、最初にダミアンさんから「生命・細胞」といったテーマが提案されたという。名和さんの方から、ダミアンさんからの提案に対してどのようなフィードバックをしたのだろう?
「“cell”というコンセプトを最初にダミアンから聞いたとき、ダンサーに対峙するコンセプトとしてはもうすこし何かが必要だなと思ったんです。ダミアンが見てくれた《Foam》という作品でもゼロから立ち上がろうとする泡のボリュームを表現していましたが、ちょうど自分が《Direction》というペインティングや、《Force》という作品を集中して制作している時期だったこともあり、“重力と拮抗する形状”というものに興味がありました。そこで“重力”を、セルとか身体が影響を受けるものとして、テーマにできたら面白いのではないかというアイデアを彼に伝えました。」

Foam
2013
installation view, AICHI TRIENNALE 2013, Aichi
courtesy of Aichi Triennale 2013 and SANDWICH
photo : Nobutada OMOTE | SANDWICH
『VESSEL』の舞台美術として舞台上に登場する、まさに“器”のような白い造形物のなかには、固まったり液状になったりする可変的な素材が使われている。ダンサーの身体と絡み合い、舞台のなかでも大きな役割を果たすこの素材について、名和さんに聞いた。
「素材に関しては、肉体のように変化することや、流動性があるものが良いなと考えていました。ソリッドな素材感だけで舞台美術をつくるのは、この作品に対してはすこし固すぎると思ったんです。液体と固体、その間にあるようなものが必要でした。それが生命や、身体に対する比喩的な表現になったらいいなと思っています。生と死、エロスとタナトスといったものが同時にあり、それが表裏一体になっているような関係を、イメージで伝えられるものを探し、今の素材に辿りつきました。ダミアンに見せたら、とても気に入ってくれて、使うことになったんです。」
彫刻作品の創作と舞台美術の違い
名和さんは多様な素材とテクノロジーを駆使しているアーティストだ。舞台美術の創作と、いつもの彫刻やインスタレーションの創作は、名和さんにとってどのような違いがあったのだろう?

PixCell-Deer#24
2011
collection of The Metropolitan Museum of Art, New York, USA
courtesy of SCAI THE BATHHOUSE
photo : Nobutada OMOTE | SANDWICH
「あんまり変わらないですね。彫刻とかインスタレーションをつくるときもいろんな与条件を考慮してつくるので、建築のプロセスにも近いし、彫刻的でもあります。創作のプロセスとしては、僕自身の頭のなかでイメージをしたものを造形にするという点では同じでした。ただ、舞台作品の慣例では、搬入期間がとても短かったり、時間軸がある表現としてシーンをどんどん展開した方が良かったり、といったふだんは経験しないこともたくさんありました。それは面白い面もあれば、難しいと感じる面もあります。
彫刻やインスタレーションは、一度展示したら長期間同じ設定で見てもらうことができる場合がありますが、舞台の場合は作品が目の前でみるみる変わってゆき、しかも生身の身体がそこでうごめいています。その変化の度合いを考えると、彫刻よりもずっと大きな変化があるので、とてもぜいたくな空間なんだなと感じています。」
『VESSEL』のコラボレーションと今後の展開
ゴールを設定せずにはじまり、今後も続いていく感覚があると名和さんが語る『VESSEL』でのコラボレーション。この取り組みにはどこか到達地点のようなものはあるのだろうか?
「ダミアンとのコラボレーションは、とても面白かったですね。次にロンドンで上演しようという話をしていますが、そこでもまた表現の飛躍が起こればいいなと思っています。ダミアンもこれからやりたいことがいっぱいあって、会うたびにいろんな構想が出てくるので、ダミアンとの付き合いはまだまだ続きそうだなという予感はしています。
僕もこれを単なる舞台と捉えるのではなくて、『VESSEL』というプロジェクトから派生したものが、自分の彫刻とかインスタレーションとしても作品になっていったら良いなと思っていて、その計画はいろいろ考えているところです。ダンサーのポーズを3Dでスキャンして、彫刻にしていく作品も今年は進めていく予定です。」
『VESSEL yokohama』に向けて
大阪、京都、犬島とすこしずつ変化しながら公演を繰り返し、各地で大きな反響を呼んできた『VESSEL』。2017年最初の公演となる1月26日からの横浜赤レンガ倉庫1号館での上演には、名和さんはどのような期待をもっているのだろう。
「京都のロームシアターの公演と比べると、横浜赤レンガ倉庫1号館の会場は半分ぐらいの空間で、ダンサーと鑑賞者がかなり近くて、肉薄したような迫力が出ると思います。作品の生々しい部分が、京都のときよりも出るのではないでしょうか。」
会場のスケールに応じて、作品の印象の変化も楽しめる『VESSEL』。最後に『VESSEL yokohama』の観客にメッセージをいただいた。
「意味や記号といったものに縛られずに、先入観もなく、自由に観て感じてもらえたらうれしいです。ゼロから体験してもらう想定でつくっているので、何も考えずに、まずは作品を体験してください。」
多忙を極めるスケジュールの合間をぬってスカイプインタビューに快く応じてくださった名和さん。いくつもの建築やアートのプロジェクトが同時進行していて、いつも頭のなかはアイディアでいっぱいだと語る。名和さんのスタジオ「SANDWICH」から生まれるこれからのプロジェクトも楽しみだ。
(文・及位友美/voids)
【プロフィール】
名和晃平(なわ・こうへい)
彫刻家。1975年大阪府生まれ。京都を拠点に活動。京都造形芸術大学大学院芸術研究科教授。1998年京都市立芸術大学美術学部美術科彫刻専攻を卒業。2000年同大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。2003年同大学大学院美術研究科博士課程彫刻専攻修了。2011年東京都現代美術館で個展「名和晃平‐シンセシス」開催。ビーズやプリズム、発泡ポリウレタン、シリコーンオイルなどの現代的な素材を用いて、彫刻の新たな可能性を切り拓く。2009年より京都にて、建築家、デザイナーなどのクリエイターと、横断的な創造活動を行うプラットフォーム「SANDWICH」のディレクターをつとめる。
【イベント概要】
横浜ダンスコレクション2017
公式ホームページ http://yokohama-dance-collection.jp/
会期:2017年1月26日(木)~2月19日(日) 計25日間
会場:横浜赤レンガ倉庫1号館全館及び屋外広場、横浜にぎわい座 のげシャーレ
ダミアン・ジャレ | 名和晃平 『VESSEL yokohama』
http://yokohama-dance-collection.jp/program/program01/
日時:2017年1月26日(木)19:30~/27日(金)19:30~/28日(土)16:00~/
29日(日)16:00~
会場:横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール
住所:神奈川県横浜市中区新港 1-1
アクセス:
桜木町駅(JR京浜東北・根岸線・市営地下鉄ブルーライン)より徒歩 15 分
関内駅(JR京浜東北・根岸線・市営地下鉄ブルーライン)より徒歩 15 分
馬車道駅または日本大通り駅(みなとみらい線)より徒歩 6 分
振付:ダミアン・ジャレ
舞台美術:名和晃平
音楽:原摩利彦(特別参加:坂本龍一)
出演:森山未來、エミリオス・アラポグル、浅井信好、森井淳、皆川まゆむ、三東瑠璃、
戸沢直子
照明:吉本有輝子
音響:福原吉久
舞台監督:尾崎聡
*本公演のチケットは完売いたしました。(当日券の販売もございません。)
料金:前売 3,500円、当日 4,000円、U-25 3,000円
※全席自由・税込
※U-25:前売りのみ販売/公演日時点で満25歳以下の方が対象(入場時要身分証)
※未就学児の入場はご遠慮ください
※やむを得ない事情により出演者や演目が変更となる場合がございます。