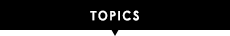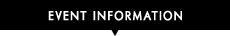審査員の心を捉えたポジティブな建築提案
建築界のオリンピックとも言われるヴェネチアビエンナーレ国際建築展。毎回出展国がそれぞれに社会の課題を取り上げ、建築が果たす可能性を探る意義深い展覧会として知られている。第15回目となる2016年は63カ国が参加し、5月28日から11月27日まで開催されている。

第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展の日本の展示会場。
災害、貧困、移民、高齢化、少子化、違法建築…と今回も世界からたくさんの問題が寄せられた中で、日本が提示したのは「現代社会のコミュニティの希薄さ」に対する解決案。
「en (縁):」というコンセプトで12組の建築家が「縁を紡ぐ」建築の実践を具体的に見せた。西田さんは中川エリカさんと一緒に2009年に手がけた「ヨコハマアパートメント」を出品。外部に開かれた共有土間つきの2階建て4世帯の集合住宅で、注文したのは横浜の創造都市プロジェクトを推進した人物だった。
「駅から徒歩15分の住宅街の真ん中で、利便性はよくない。だから建築に特徴や魅力があって、住み方に対する提案が必要だとリクエストされました。少子化、高齢化や独身世帯の増加によって自治会の力も弱くなっている昨今、小さくても地域に活力と新しい関係性をもたらす建築、と考えたらこのかたちになったのです」

ヨコハマアパートメント。1階の共有スペースの土間から階段で4つのアパートに入る仕組み。
写真家がそこに住んでいたときは土間で展覧会を、音楽家は演奏会を、近所のおばあちゃんが亡くなったときには遺品の展覧会をした。パーティーやワークショップも開催。それほどあらたまらなくとも地域の少し大きめの応接スペースとして、気軽に集える場所となった。
「過去のビエンナーレを見ても、社会問題のクローズアップとなると、展示が状況的説明だけに終わりがち。そんな中、日本館が評価されたのは、どの建築もポジティブに実践しながら課題に取り組んでいたからだと思います。展示内容に明るい希望が感じられたからではないでしょうか」
ちなみにミラノサローネでのMINIの展示テーマは奇しくも「縁」よりもっと濃密な関係性を表す「Do Disturb(干渉し合う)」。MINIが車の「空間活用」のアイデアを生活の現場にも応用できると証明したこの展示は、シェアよりも一歩積極的に居住空間で混ざり合う仕掛けに満ちている。日本の住宅建築が昔から培ってきたノウハウを活かして、パーソナルな空間と公共空間をスイッチングしながらどちらにも出現する家具、埋め込み式でコンパクトに収納された家電など、新しい都市型ハウスユニットを提案した。

これからの住み方を提案するアイデアが注目されたMINIの展示会場。
「この展示を引き受けることになって、日本の知恵は世界から注意深く観察されていると感じました。“シェア”を一歩進めた“混ざる”は、今後の大きなテーマとなっていくでしょう。コミュニティの再生、異なる民族、文化、世代をどうやって上手に混ぜるのか、そんな課題に対して、建築やデザインが果たす役割は大きいと考えています」
“パブリック”の考え方
地元横浜で西田さんが関わっているプロジェクトのひとつが、横浜DeNAベイスターズが進めている「コミュニティボールパーク」化構想。横浜に来る観光客にアンケートを取ると、横浜スタジアムの知名度は高いのに、実際に行ったことがないという人が多い。そこで野球に関心がない人でもスタジアムや隣接の横浜公園を利用してもらえるように、賑わいを創出していこうというプロジェクトだ。スタジアムのチケットショップの横にカフェ・スペースを作ったり、外からグランドの練習風景が見渡せるフォト・スポットを設置したり、公園と一体となった新たな楽しみを提供している。


市民に人気のあるフォト・スポットとカフェ。
「スタジアムで試合がある日は、このエリアには約28000人もの人が訪れます。28000人というと漠然としてイメージが掴めないけれど、自分や家族が野球を見るだけでなく、ここで楽しむなら? というイメージは抱くことができる。だから自分の実感を大切にして考えます。例えば朝グラウンドで気持ちよくキャッチボールしてから出勤してみたい、仲間や家族とワイワイ野球を見るのに相撲のマス席のようなものがあるといいな…そんなあったらいいな、を集めて実現してきました」
球場の観客席にパーティーBOX席やバーカウンター付きなど、観戦+αのバリエーションを持たせることによって、スタジアムの入場者数はここ4年間の間になんと65%も増加した。そして、横浜公園と日本大通りの角にリニューアル・オープンする歴史的建造物の旧関東財務局ビルには「スポーツ×クリエイティブ」の創造拠点が誕生する。

旧関東財務局ビル。歴史的建造物の新しい活用例として期待がかかる。
「スポーツのいいところは何にでも結びつけられることです。すぐに思いつく健康、ファッション、食だけじゃなくて、少し街を走ると都市観光もできるわけだし、クリエイティブと結びつけると、経験のない人でも楽しめる新しいスポーツも生み出せる。ユルスポというチームとコラボして、横浜の中小企業に眠っている道具や製品で新たなスポーツを作る話も進んでいます。ビルから横浜公園や日本大通りに出て、健康にいいことが町中でできるようになる。若い人には“今から予防医療”と言ってもピンとこないけれども“まちを遊び尽くそう”と呼びかけた結果、気がつくと長きに渡って健康的な生活が実現できていた…そういうまちづくりがしたいのです」
西田さんは「28000人全ての気持ちがわかるとは思っていないし、全体を俯瞰したいとも思わない。ひとりひとりの楽しむ実感が集まって全体が作られると考えています。僕自身もその中のひとりです」と言う。
「まちも同じです。中心にみなが集まる単一中心型より、様々なライフスタイルの拠り所があちこちにある多中心型のダイバーシティの方が断然面白い! 賑わいつくりにしても、その場所を使い尽くすアイデアや人材を集めて、対話しながら進めていくと、徐々に賑わいにつながっていくと思うのです」
西田さんが影響を受けた人物に、デンマークの都市計画家のヤン・ゲールがいる。1980年代から25年間をかけてコペンハーゲン中心地にストロイエと呼ばれる歩行者天国を広げて、車弱者である子ども達や高齢者をまちに呼び戻し、新たなまちの魅力を創造した人物だ。
「“私たちがまちを作り、そのまちが私たちを作る”とゲールは言っています。まちは育てていけばいいのです。自分が所有していないもの以外はパブリックという概念で、そこもちゃんと自分の暮らしの延長で考えていこうとする姿勢がまちでの時間を豊かにし、ひいてはまちをよくしていくのではないかと思います」
このまちに住んでよかったと思うことは、自分がコミュニティに共感している証拠。つまりそれがパブリックライフの充実ということなのだ、と西田さんは考えている。
「建築界は今、静かなる衰退期。それでも…」
西田さんの事務所は共同設計を軸としており、自分の設計のパートナーに若い世代を選ぶことが多い。
「40代の僕と20代のスタッフでは、生きて来た時代、社会的環境、触れて来た情報が違います。未来に対してボールを投げるのが建築の価値だとすると、若い人の実感の方がよりリアルですよね」
しかし今、建築は静かなる衰退期に入っている。経済が上向きの時代、人口が増加中の時代、インフラの足固めの時代、建築は求められた。公共的な建築物を作ることは圧倒的な「善」だった。だが爛熟の時を迎え、都市や社会の成長が滞っている今、建てることは必ずしも生産的であるとは言えなくなった。建てる意味をまず問う機会が多くなった。
「建築界全体が迷っていると思うのです。それは後進にも伝わり、大学では学生が作る論理に非常にこだわるようになりました。例えば学生に“1000平米の敷地に劇場を建てる”という課題を出すと、“人口減少の今、建てる必然性があるのか?”とか“作ったものでさえどんどんなくなっているのに”というコメントが返ってきます。そう問われれば、教える方にも明確な答えがあるわけではない…」
「それでも」と西田さんは続ける。「建築物を通して人の生き方、まちの営みを考えられる建築という仕事は素晴らしい! と彼らに声を大にして言いたい。ヨコハマアパートメントはわずか150平米の小さな建物ですが、都市に対するインパクトを持っています。人の暮らしと等身大のものを設計して、まちや人に喜びを与える喜びを感じて欲しいと思っています」
企画だけでなく、とにかく実践し、そこからフィードバックすることの大切さも力説する。
「建築は、実現したものを通して評価や効果を測定し、使われることに大きな意味があるからです。机上の空論ではダメ」
オンデザインでは、優れた建築物に泊まる社員旅行を毎年行っている。クライアントが自分の好みを開陳する時にお気に入りの場所を語ることがあるが、そこに行ったことがあるのと全く知らないのとでは理解に雲泥の差がある。だから若き建築家を彼らではなかなか泊まれない高級な場所に連れていく。
「経験や記憶は確実に身に付きます。自分の若い頃、先生やクライアントからお金では測れない価値の経験をさせてもらったことをとても感謝しています。だから若手にも実践や体験を重ねてもらいたい。そして、彼らの世代の価値観を建築にアウトプットして欲しいのです」
「まあ、そこだけ。実際はスタッフにおんぶにだっこのダメ社長なんですけど…」と西田さんは照れくさそうに笑う。

関内エリアにあるオンデザインパートナーズのオフィスで。
横浜のプロジェクトの話を聞いている時も思ったが、関わるのは、建築にしろ、まちにしろ、人にしろ、この人は生粋のプロデューサーだ。育てていく、作り出していく役割を担う人だ。ゲールは著書の中で、建築も都市も、装飾や技術ではなく、本質は人のための空間を作ることだと言っている。全てを自分の実感に落とし込んで考える西田さんだからこそ、本来の人間のサイズの喜びを創出できるのではないか。その様々な喜びが集積する場を「まち」と呼ぶことができれば、こんなに素敵なことはない。
(文・田中久美子)
国際交流基金「第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展」:
https://www.jpf.go.jp/j/project/culture/exhibit/international/venezia-biennale/arc/15
「コミュニティボールパーク」化構想:
http://www.baystars.co.jp/event/stadium/
ondesign partners:
http://www.ondesign.co.jp