※本記事は旧「アートウェブマガジン ヨコハマ創造界隈」2011年6月25日発行号に掲載したものです。
第12回:鑑賞ということ、あるいは美術館
展覧会、まずは「キャプションを読む」派? それとも「鑑賞」派?
非常勤で教えている大学で、鑑賞論という授業を持っている。文字通り、美術作品をいかに鑑賞するか、ということを学ぶための授業である。毎年、最初の授業のときに、美術に興味があるであろう(何と言っても美大で、しかも芸術学を専門としている)学生に、美術館に展覧会を見に行った時、作品よりも真っ先にあいさつや、解説、あるいは作品の横に置かれている作品のタイトルなどが記されたキャプションをまずは“読む”派と、あらゆるテキストは無視して作品そのものを“鑑賞”する派に分かれてもらうことにしている。学年にもよるが、九割以上の学生が、何らかのかたちで、まずはテキストを読む行為から作品鑑賞に入るという。恐らく、こうした美術を専門に学問しようとしている学生でなくとも、同じような結果が出るだろう。その理由については後述する。
ところで、展覧会場の作品の傍に、今や当たり前のように鎮座するキャプションだが、こうした習慣が誕生するのは、ルーブル美術館といった美術館がヨーロッパを中心に次々と誕生した18、19世紀以降のことだ。美術作品と、言わば不即不離の関係に及んでからせいぜい150数年くらいしか経っていないわけだ。
この頃の美術館では、膨大に収集された所蔵作品の同定作業が同時に開始された。同定作業、つまり、この絵画は、間違いなく誰某の作品であること、何年に制作されたかどうか、これまでの持ち主についての資料に裏付けられた確証等々の作業であり、学問としての美術史にとって、美術作品を歴史化するために避けることはできない。
さて、件の学生を、美術を鑑賞するに当たっての異なる行為の二派に分けて終わり、というわけではない。次に、確認のために、作品鑑賞の筆頭に位置するまずは作品のキャプションの項目を列挙してみる。
作家名/作品名/制作年/所蔵先
といったところが、キャプションに記される主な項目である。とは言え、これらの情報は、作品の情報の氷山の一角であって、美術館側には、
材質・形状/展覧会歴/修復歴/収蔵の属性(購入か、寄贈か、寄託か)/これまでの所蔵歴/購入額/保険評価額/等々
といった普段は公開されない情報が保管されている。
さて、これらの項目を列挙したときに、何か他に想起される類似のモノはないか、と尋ねるのが、この授業の本当の狙いである。例えば、ペットボトルが手元にあれば、さて、この商品の作家名に該当するものは?すなわち製造会社名、制作年は?製造年月日(はたまた賞味期限も!)、材質・形状は?材料表示からカロリー表示まで。
事程左様に、美術作品を同定するための諸条件は、今や市場にあふれる商品を「間違いないモノ」として購買する条件を十分に満たしている、という言い方も可能ではないか。ついでながら、今でこそ、商品の追跡可能性あるいは流通全体の情報の追跡可能性として使われるトレーサビリティに至っては、すでに美術作品では、その入手歴として当初から重要な項目として設定されていた。とりわけ、美術作品の場合、その歴史が数奇な運命を表象するものであれば、そこに新たな付加価値が添えられる事になるのだ。
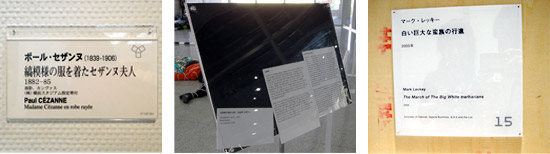
キャプションは商品情報だ!?
19世紀は、美術をとりまく環境が、「アカデミック・システム」から「画商・批評家システム」へシフトした時代だった。かつて美術作品にキャプションが必要でなかったのは、それが、共同体の共有すべき記憶の表象であったからに他ならない。神話・歴史・宗教といった主題を金科玉条としたアカデミック・システムが崩壊し、美術家は、急速に変化する現実にその主題を求めはじめ、同時にモノとしての美術作品は、市場の原理に巻き込まれる事になった。それから、美術史という学問大系が19世紀に確立されたこともまたキャプションというプレゼンスを要請したもう一つの要因でもある。先ほど述べたように、美術史というのは、何よりも対象とすべき美術作品の氏素性を明らかにすることで担保される学問である。誰が、いつ、どこで制作したのか判然としないモノは、真正の美術作品として認定することはできないのだ。
この姿勢は、何かに似てはいまいか?
19世紀は、都市、この場合近代都市が誕生する時代でもあった。産業の拡大、労働人口の急増によって、異なる文化、慣習、宗教を背景とした人種が混在する時代をも意味していた。ミッシェル・フーコーが指摘するように、国家が、国民を様々な側面(犯罪、病、あるいは‘生’そのものをも)で管理をするための新たなシステムを生み出した時代でもあるのだ。つまり、人の素性を明らかにし、戸籍化し、管理するシステム。ついでながら、写真の登場が、犯罪者の同定を容易にすることで、犯罪学に大いに貢献したことは良く知られている。存在の証を詳らかにする事で、予断を許さない事態を回避するシステムの中に、写真も、そして美術史もまた加担しているというわけだ。
人と人とのコミュニケーションが、お互いの氏素性を明らかにされなければ保証されない時代。本来であれば、感性に訴える美術が、感性で応えるのではなく、テキスト化された戸籍簿を前提に「鑑賞」が成立するシステムを、今や何の疑問もなく受け入れている事態について再考する意味はありそうだ。
とは言え、現実は、何の表示もないペットボトルの液体を、誰が手にし、口にするだろうか?と我々に問いかけてくる。いきなり作品自体を何らテキストの補助なしに鑑賞する、といった行為は、危険でむしろ避けるべき行為なのかもしれないのだ。何の表示もないペットボトルの液体をいきなり飲む行為と似て。そして、展覧会を訪れて、作品を鑑賞することは、その作品の揺るぎない芸術的価値の確証を保証するテキスト「鑑賞」から始めなければならない。先に学生ばかりか、ほとんどの人が、美術館の展覧会鑑賞を、テキストを読むことからはじめるだろうと言った所以だ。こうした行為は、言い換えれば、作品の周辺に布置されたテキストが、作品のメタテキストとして十全に機能している証左でもある。
「生の表象」としての現代美術と「死の象徴」としての美術館
:第4回ヨコハマトリエンナーレ、もうひとつの見方
さて、今日、歴史に名を残すであろうと目されている美術家が、その作品の展示場所として美術館を全く念頭に入れないことはおよそ考え難い。というよりも、美術作品は、美術館の壁面、あるいは展示空間を念頭に制作されていると言っても良いだろう。近代絵画が、「展示空間—壁面—を内在化し、これを表象し始めたのである。」と指摘したのはアメリカの美術史家ロザリンド・クラウスだが、まさに近代美術は、作品が、美術館の壁面の表象として機能する歴史でもあったわけだ。ところで、1871年に生を受けたポール・ヴァレリーとマルセル・プルーストが、美術館を巡って興味深いテキストを残している。尤もこのことを最初に紹介したのは、アドルノの「ヴァレリー プルースト 美術館」(1953)であるのだが、それにしてもまるで当たり前のこととして認識している「美術作品と美術館」の関係に意外な落とし穴があったことを彼らが示唆してくれているのはやはり傾聴に値する。アドルノは、ヴァレリーの美術館への言及をこう紹介している。
「物が眩暈がするほどルーヴルに溢れかえっていることと明らかに係っている。自分は美術館をそれほど好いていないとヴァレリーはいう。あんなにもたくさんの驚嘆に価するものが美術館に保存されているのに、味わいあるもの(das Köstliche)ときたら、まことに寥々たるものだ。貴族じみたヴァレリーは、彼から散歩用のステッキを取り上げる美術館の横柄な態度や、喫煙禁止の掲示によって、すでに自分が圧迫されていると感じるのだ。・・・・なぜ自分がやってきたのか、人々にはわからない。教養をつけるためか、陶然としてみたくてか、それとも、習慣に従うという義務をはたすためか。・・・このような支離滅裂な館は、いかなる快楽の文化も、いかなる理性の文化もつくりえなかっただろう。死せる幻想がそこには安置されている、と彼はいう。」
冒頭で指摘したように、まずは解説やキャプションを読み始めるところから鑑賞を開始するテキスト派は、結局のところ美術を教養して受け入れ、それをして鑑賞と位置づけてしまっているのだ。
あるいは、
「作品の永続は、《今とここ》によって計られる。ヴァレリーにとって芸術は、直接的な生のなかの場所を、すなわち、かつてそれがそのなかにあった機能連関を失ったときに滅びるのだ。つまり、使用する可能性と関係を失ったときには滅びるのである。」と。これは、卑近な例で言えば、元々あった寺社ではなく今では博物館に収蔵されている仏像を想起すれば良いだろう。あるいは、無縁墓地のような存在としての美術館とでも言うべきか。
プルーストについてはこうだ。
「言葉少なに彼は駅を美術館に比す。両所とも、行動の対象としての習慣的な表面的関連からまぬがれているばかりか、さらにこうも付け加えられるだろう、と彼はいう。両所とも死のシンボルの担い手なのだ、と。旅ということと絡まって太古から死の象徴である駅、芸術家の作り出した作品に、すなわち「新クシテ、イズレハ滅ブ宇宙」」にかかわる死の象徴としての美術館。」ヨーロッパの多くの主要駅が、いわゆるグランド・セントラル・ステーションであることを考えれば、まさに終着(terminal)に生と死を共存させる表象であるのだろう。この意味では、まさに駅そのものをリノベーションして開館したオルセー美術館は、誠に皮肉な存在を体現してしまっていることになる。
さて、後一ヶ月もしないうちに、第4回横浜トリエンナーレは開催される。そして、4回目にして、主会場に横浜美術館が使用されることになった。「生の表象」としての現代美術と「死の象徴」としての美術館は、果たして幸福なる婚姻関係を結ぶことができるのか?そこに鑑賞者は、どういった関係において参加することになるのか。今一度、鑑賞と美術館について考えてみるチャンスでもある。
参考図書
ロザリンド・クラウス「オリジナリティと反復―ロザリンド・クラウス美術評論集」小西信之訳(リブロポート、1994年) テオドール・アドルノ「プリズメン―文化批判と社会 」渡辺 祐邦, 三原 弟平訳 (ちくま学芸文庫、1996)


photo:K. Boo Moon
著者プロフィール
天野太郎[あまの たろう]
横浜美術館主席学芸員。横浜トリエンナーレ組織委員会事務局
キュレトリアル・チーム・ヘッド。
※本記事は旧「アートウェブマガジン ヨコハマ創造界隈」2011年6月25日発行号に掲載したものです。

















